インドネシアのキリスト教系の葬儀・火葬事情をご紹介します。インドネシアの火葬事情と言っても、インドネシアの主流は「土葬」です。インドネシアは世界で最もイスラム教徒の数が多い国として知られています。イスラムは土葬なのです。そのため「インドネシアの火葬?」と不思議に感じる人もいるかもしれません。
しかし、あまり知られていないことですが、インドネシアでも「火葬」が増えてきているようです。「いったい、どういうこと?」と思うかもしれませんが、今回注目したいのはインドネシアの華人(中国系の住民)社会です。
彼らの多くはクリスチャンであったり仏教徒であったりします。かつて親の世代では土葬を選択してきた家族でも、近年になって火葬を選択する人の割合が増えていると言われています。
そこで今回は、「インドネシアの火葬と葬儀」をテーマにブログにまとめてみました。あまり知られることのないインドネシアのキリスト教系華人の葬儀・火葬事情をご紹介しましょう。次の3部構成でお届けします。
| タイトル | |
|---|---|
| 第1部 | インドネシアの葬儀|非イスラムのキリスト教系の葬式と火葬の内容は?(本ページ) |
| 第2部 | インドネシアで火葬場見学|東ジャワ・マランのキリスト教華人の場合 |
| 第3部 | インドネシアの火葬事情|イスラム土葬文化で火葬が選ばれる背景と課題 |
なおキリスト教でも、カトリックとプロテスタントでは葬儀の式次第が違うので、今回はカトリックの事例を取り扱います。
目次
インドネシアにおける火葬文化とは?

インドネシアで有名な火葬文化というと「バリ島」です。バリ島の王族の葬儀は世界的にも有名で、日本でもテレビで紹介されることがあります。バリ島の場合は火葬です。
「インドネシア全土が土葬文化であるにもかかわらず、なぜバリ島だけが火葬?」と思われるかもしれません。その理由は、バリ島の人口の約95%がヒンズー教徒で占められているという事実が影響しています。
インドネシアの火葬といえばバリ島が有名

そのため、インドネシアで火葬というと「バリ島」だけが注目されがちです。調べたところ、火葬に関する日本の業界団体が「研修視察」としてバリ島へ行くこともあるようです。リゾート地としてではなく、本格的に火葬が行われている場所としても注目されているわけです。
これは私自身が2013年11月にバリ島を訪れた際、偶然にも見学ができたものですが、現地の王族のお葬式の様子です。火葬の前に、これだけ大規模なお祭りが行われていました。
なお、バリ島の火葬を取り上げた作品はたくさんあるようですが、例えば『土と火と水の葬送-バリ島の葬式』(1990年:114分)があります。国立民族学博物館、民族文化研究部の大森康宏教授が監督となって、映像化されたものです。
バリ島以外のエリアでも火葬の需要が上昇している

一方で、バリ島以外のエリアでも、例えば首都であるジャカルタ(Jakarta)や、インドネシア第2の都市スラバヤ(Surabaya)といった大都市には火葬場があります。
これにはインドネシアに住む外国人の利用も念頭に入れられているようです。例えば、ジャカルタにある日本大使館のウェブサイトを見ると、「火葬 (御遺骨を本邦に持ち帰る場合)」というページがあります。いざという場合は、現地で火葬してから日本に送るという体制ができているわけです。
なお、ジャカルタとスラバヤの位置は、地図で示すと以下の通りです。
しかし、特に近年になってから顕著になっているのは、バリ島以外においても火葬の需要が増えているということです。これは「インドネシアに住む外国人」の死亡者が増えたというわけではありません。インドネシア現地でも需要が増しているのです。
イスラム教の場合は宗教上の理由から土葬が選ばれますが、例えばクリスチャンであれば土葬にこだわらない動きが出ています。そのひとつがインドネシアの華人です。しかしこうした実態はあまり知られていないように感じます。
つまり、「イスラム=土葬」という先入観があるためか、バリ島以外での火葬事情は意外と知られていないというのが実情なのです。なお上の写真は、ジャワ島東部のマランにある火葬場です(詳細は後述します)。
火葬の学会「火葬研」で大賞を受賞した先生との共同調査!
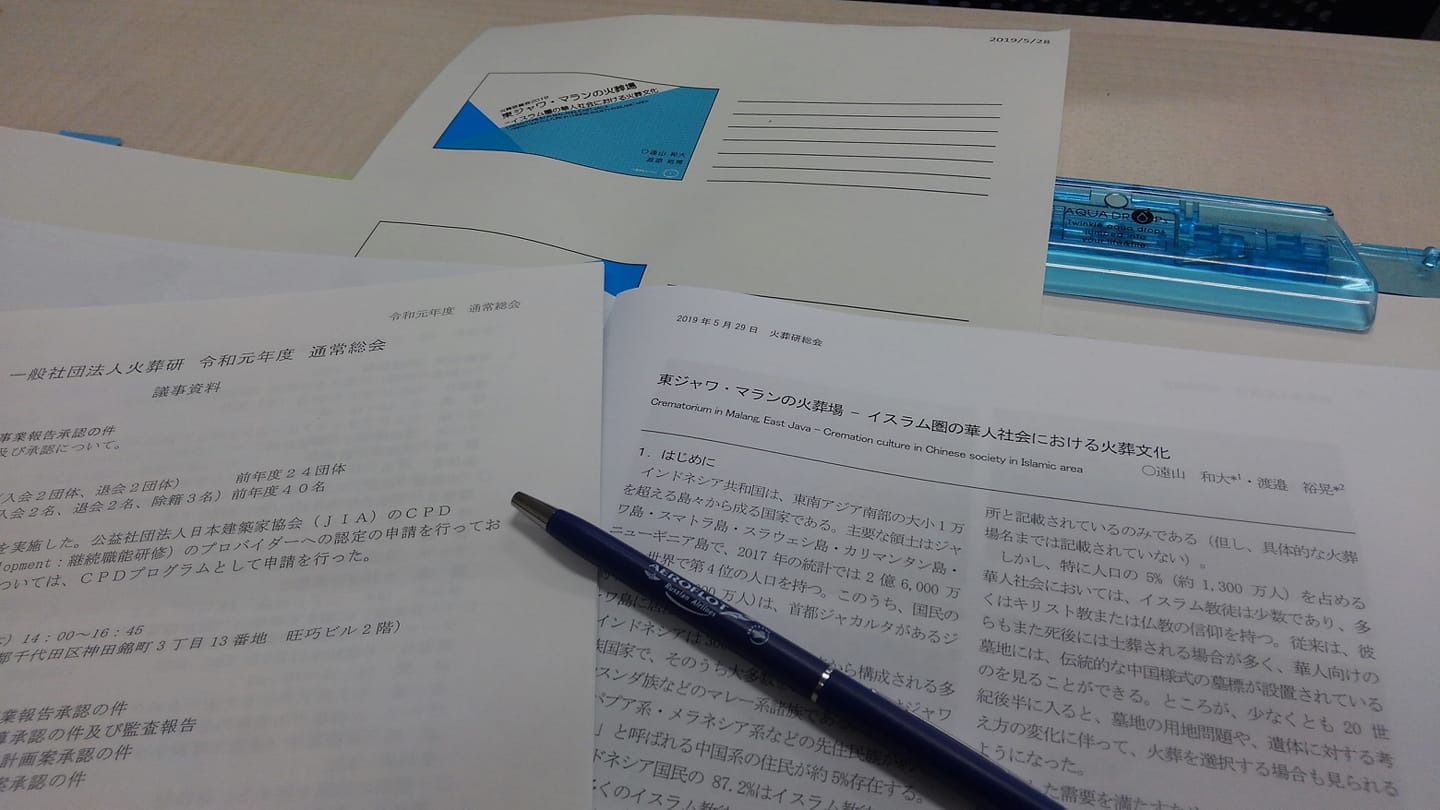
インドネシアにおける華人・キリスト教系の葬儀や火葬の事情について紹介する前に、まずはこのブログ内容の背景からお話しさせて下さい。今回のブログでご紹介するものは、火葬に関する調査研究を行う学会「火葬研」で2019年5月29日に報告された内容が元になっています。
題名は「東ジャワ・マランの火葬場 – イスラム圏の華人社会における火葬文化」(Crematorium in Malang, East Java – Cremation culture in Chinese society in the Islamic area)というものです。
火葬研究で知られる富山大学の遠山和大先生

2018年の「火葬研」学会発表で、大賞を受賞された富山大学の遠山和大先生との共同調査により実現しました。遠山和大先生とは30年来の関係です。私が住む東ジャワ・マランの環境を気に入ってくださり、よくお目にかかります。そうした対話の中で今回のテーマを思いつくことができました。
その後、実際にマランの火葬場を調査することで、今回のとりまとめが実現したわけですが、そういう意味で言えば、「インドネシアにおける火葬」は専門家が注目したくなるテーマでもあるということです。その背景には前述の通り、「まだ意外と知られていない」という点があります。
インドネシアの火葬研究は今後の課題
火葬研究で有名な機関といえば、イギリスにある火葬協会(The Cremation Society)です。同団体は世界の火葬場の状況をまとめていますが、インドネシアの火葬場のデータを見ると2017年現在で7ヶ所あるとしています。
具体的には、ジャカルタ、スラバヤ、バンドン、ジョグジャカルタ、スマラン、マラン、スラカルタの7ヶ所としています。この7都市はいずれもインドネシアの中心とでも言うべき「ジャワ島」です。さらには「No further information」としており、場所以外の詳細な情報は不明としていることから、インドネシアの火葬場について、ほとんど把握されていないと言えるでしょう。
実際にはヒンドゥー教が多数を占めるバリ島にも火葬場は存在し、今回紹介するマランでも火葬場は2ヶ所あります。つまり、世界的な機関でもインドネシアの火葬場の状況は把握しきれていないことがわかります。
後述するように、「インドネシア=イスラム」というイメージもあって、インドネシアにおける火葬の研究は、ヒンドゥー教が多数を占めるバリ島での文化研究にとどまっていました。イスラム圏における火葬の実態は、まだまだ研究が不足している状況だと言えるでしょう。
なお、ここにまとめたものは調査結果の「メモ」という位置づけです。そのため今後加筆や訂正などを行う可能性があります。また、これを元にブラッシュアップさせ、その後、正式な論文として発表される予定になっています。というわけで「火葬研」での発表内容にもとづき、ご紹介します。
本ブログ「インドネシアの葬儀|非イスラムのキリスト教系の葬式と火葬の内容は?」と、続編となる「インドネシアの火葬場|イスラムの土葬文化で華人に選ばれる背景と特徴」の2部構成でお届けします。
インドネシアの特徴は?
まず初めにインドネシアの概要を簡単にご紹介します。すでにご存知の方は読み飛ばしていただいても構いません。また「もっとインドネシアのことが詳しく知りたい!」という方には、共著で執筆した上の本を参考にしていただければ幸いです。
インドネシアという国家と人口

インドネシアは、東南アジア南部の大小1万を超える島々から成る国家です。主要な領土はジャワ島・スマトラ島・スラウェシ島・カリマンタン島・ニューギニア島で、2017年の統計では2億6,000万人と、世界で第4位の人口規模になっています。このうち、国民の約半数(1億4,000万人)は、首都ジャカルタがあるジャワ島に居住しています。
人口だけでなく面積で見ても規模が大きく、インドネシアの国家の広さは日本の5倍になります。世界有数の群島国家として、島の数の多さでも有名です。
多民族国家インドネシア

インドネシアは300を超える民族から構成される多民族国家としても有名です。そのうち大多数を占める約7割はジャワ族やスンダ族などのマレー系諸族になります。それ以外には、パプア系・メラネシア系などの先住民族が約26%、「華人」と呼ばれる中国系の住民が約3%程度存在します。中国系の華人がかなりの少数派であることがご理解いただけるかと思います。
インドネシアは多民族で構成されるため、言語の数も多いことで知られています。公用語は「インドネシア語」ですが、それぞれの地方に特有の「地方語」が存在します。
また今回紹介する中華系のインドネシア人の場合、中には中国語ができる人もいます。「インドネシアで漢字?」と驚かれることもありますが、そうした背景から葬儀場や火葬場、墓地においても、漢字表記を見つけることができます
インドネシアにおける宗教の分布

インドネシア国民の87.2%はイスラム教徒で、世界で最も多くのイスラム教徒人口を抱える国となっています。インドネシアはイスラム教徒の数で世界ナンバーワンなのです。
イスラム教以外では、プロテスタント(7%)とカトリック(3%)を併せたキリスト教徒が約1割で、ヒンズー教徒が1.6%、仏教徒が0.7%となっています。
| 宗教 | 人口比率 |
|---|---|
| イスラム教 | 87.21% |
| キリスト教(プロテスタント) | 6.96% |
| キリスト教(カトリック) | 2.91% |
| ヒンドゥー教 | 1.69% |
| 仏教 | 0.72% |
| 儒教 | 0.05% |
但し、地域によって宗教の分布が異なっているのが特徴です。
スマトラ島やジャワ島ではイスラム教徒が大多数を占める一方、カリマンタン島およびスラウェシ島ではイスラム教徒とそれ以外が半々程度。ニューギニア島ではイスラム教徒が1割程度となり、キリスト教徒(主にプロテスタント)が大きい勢力を占めているという現状があります。
また、ジャワ島の東隣に位置するバリ島と、カリマンタン島の一部では、現地の伝統的な信仰と習合したヒンズー教の信仰が多数を占めています。
ちなみにインドネシアでは無宗教は非合法のため、国家が定める宗教のいずれかに属さなければいけないこととなっています。全国民が携帯を義務付けられてる住民登録カード(KTP)にも「宗教」の欄があります。
なぜインドネシアでは火葬が珍しいのか

すでにご紹介した通り、インドネシアの人々の多数派はイスラム教徒です。イスラムの場合は火葬ではなく土葬の文化になります。キリスト教徒の数や、華人の数は、インドネシア全体からすれば少数派です。そのため、まだまだインドネシアでは火葬は珍しいケースに入るようです。
インドネシアにおける土葬と火葬

インドネシアにおける火葬といえば、バリ島におけるヒンズー教徒の火葬が有名です。特に身分の高い人々が火葬される際には、大規模な祭典が催されることで知られています。その注目度の高さもあって、バリの火葬事情については、これまでにも多くの報告や研究が行われているのが実態です。
その一方で、イスラム教では火葬が禁忌・タブーであるという関係から、インドネシア国民の大多数を占めるイスラム教徒は、死後に土葬されることになります。都市部の墓地はもとより、地方の小さな村落の周辺でも、典型的なイスラム教徒のための墓を数多く見ることができます。
また、インドネシア建国の父とされるスカルノ初代大統領も土葬です。
こうした事情もあって、インドネシアにおける火葬に関しては、バリ島を除いてほとんど注目されてこなかったのです。例えば前述したように、イギリスの火葬教会の資料においても、2017年の統計では、インドネシアの火葬場数は僅かに7箇所と記載されているものの、具体的な火葬場名までは記載されていません。また、実際の火葬場の実態まで追いきれていないのはすでにご紹介した通りです。
インドネシアの華人社会が「火葬」を選択した背景

しかし、特に人口の3%(約900万人)を占める華人社会では、イスラム教徒は少数であり、多くはキリスト教または仏教を信仰しています。
元々は、彼ら華人たちも死後には土葬される場合が多かったようです。華人向けの墓地には、伝統的な中国様式の墓標が設置されているのを見ることができます。土葬を前提とする大きなサイズのお墓も特徴です。
ところが、少なくとも20世紀後半に入ると、墓地の用地問題や、遺体に対する考え方の変化に伴って、火葬を選択する場合が見られるようになっていきます。こうして次第に火葬を選ぶ人が増えているのは、すでにご紹介した通りです。
注目されずにきたインドネシアの火葬場事情とその実態

そうした需要を満たすため、インドネシアにおいても火葬場の建設が進められるようになっていきました。少なくともジャカルタやスラバヤといった大都市においては、近代的な火葬場が存在します。おそらく、前に挙げたイギリスの火葬教会の統計も、こうした大都市にある、いわゆる「目立つ」火葬場数を掲載したものと推測できます。
インドネシアにおける華人社会は大都市に留まらず、多くの地方にもその範囲が広がっています。そのため、火葬に対する需要もまた地方各地に存在するはずで、統計には現れてこない火葬場も存在するはずだと考えられます。
そうした火葬場がどのように運用されているか、また、どのような儀礼が行われているのかといった点は、私たちが調査をした限りでは、報告されているケースを確認することができませんでした。
そこで今回、2019年2月に、インドネシアの地方都市である、東ジャワ州マランにある葬儀社と、同社がマラン近郊で運営するセントン火葬場(Krematorium Sentong)を視察し、その実態を取材しました。その取材と2011年6月、および2019年1月にマランで行われた葬儀の記録に基づいて、インドネシア現地の火葬事情をまとめていきます。
地方都市マランで華人に利用される葬儀社とは?

火葬場を紹介する前に、まずは葬儀社をご紹介しましょう。今回ご紹介するセントン火葬場を運営するのが、マランにある葬儀社「ヤヤサン・ゴトンロヨン」(Yayasan Gotong Royong)です。
東ジャワ州の高原避暑地マラン
マラン(Malang)はジャワ島東部の東ジャワ州にある都市で、州都のスラバヤから南に約90kmの内陸に位置しています。人口は約85万人で、インドネシアの都市の中では18番目の規模です。
標高は500m程度と比較的冷涼な気候で、インドネシア国内では避暑地として知られています。また、多くの大学が集まる学園都市でもあり、多くの若者が集う都市としても有名です。
マランの住民の宗教分布を見ると、87%はイスラム教徒、キリスト教徒が10%(その内、カトリックとプロテスタントはおよそ半数ずつ)、そしてヒンズー教徒と仏教徒がそれぞれ1%程度となっています。また、マラン在住の華人の多くはキリスト教徒か仏教徒です。キリスト教徒や華人が占める割合は非常に小さいということがおわかりいただけると思います。
マランの葬儀社“Yayasan Gotong Royong”

マランには、華人向け葬儀を取り扱う葬儀社が複数ありますが、今回は葬儀社と火葬場の取材を依頼するべく、その一つである「ヤヤサン・ゴトンロヨン」を訪問しました。
その際には、職員のイタ・エカワティ(Ita Ekawati)さんに対応していただき、その翌日には火葬場の視察を行うことも快諾して下さいました。今回の2本のブログ記事は、エカワティさんへのインタビュー内容を盛り込んでいます。
設立の背景と名前の理由

「ヤヤサン・ゴトンロヨン」の社名を直訳すると「相互扶助財団」といった意味で、広東系華人の人たちによって1993年に設立された団体です。
中国系住民による互助・慈善団体は東南アジア各地に見られるもので、例えばタイ王国の民間レスキュー隊である「華僑報徳善堂」もその一つです。こうした団体は、中国語の名称を冠している場合が多くあります。
しかしインドネシアでは、1960年代以降に中国語の使用が制限されていた歴史があり、その関係でインドネシア語の団体名にしたとのことです。
なお、ここの葬儀場施設は利用者の増加に伴い、近くにもう1ヶ所の葬儀施設を設けています。参考までに2ヶ所をつなぐと、このようになります。
業務内容と施設の特徴は?

「ヤヤサン・ゴトンロヨン」の本部はマランの市街地にあり、敷地内には葬儀式場が複数設置されています。
「ヤヤサン・ゴトンロヨン」は、こうした式場の提供、棺や供花・葬儀に関する用具の販売、遺体の保管、遺体や遺族を送迎するための自動車、新聞への死亡広告といった、いわゆる葬祭業者としての業務を行っています。上の写真は提供サービスを一覧にしたものです。

これは間仕切りで区切られた、葬儀式場の一区画です。仕切りを取り外して複数の区画をつなげることで、より広く使うことも可能です。

これは「ヤヤサン・ゴトンロヨン」で実際に行われたキリスト教式の葬儀の様子です。間仕切りを取り除き、広い式場として利用されていることがわかります。また、さまざまな装飾も施されます。奥にあるのは白色の棺です。
お墓を用意するか、納骨堂で保管するか

同社の火葬場の隣には墓地があります。また同社の敷地内には納骨堂があります。葬儀をした後の取り扱いについては、遺族によって、お墓を設ける人もいれば、納骨堂に預ける人もいます。これは、どのような基準で判断されるものなのでしょうか。この点について解説します。
火葬後はお墓に埋めるのが普通?
ちなみに火葬後にお墓に埋めるという選択をする人はほとんどいないようです。日本では火葬後の遺骨は墓に埋めるのが一般的です。しかしインドネシアでは、火葬後の遺骨を墓に埋めるというケースは稀です。火葬した場合は、散骨をするか納骨堂に預けるかという2択なのです。
厳密に言えば、日本のスタイルは「火葬後に土葬する」という、いわば「火葬と土葬の混合スタイル」とも言えます。日本では「火葬した遺骨は墓に埋めるのが当然」と考える傾向にありますが、欧米も含め、火葬の場合は「散骨か納骨堂か」とのイメージが強いようで、インドネシアの火葬についても同様の形式となっています。
なお、余談ながら欧米でも火葬後に墓に埋めるケースはあります。「散骨する」「納骨堂に納める」「墓に埋める」の割合は不明ですが、散骨は30-50%程度のようで、火葬を推進する人たちは地中に埋められることを拒否する傾向にはあるようです。
お墓の場合

お墓を設ける場合、ほとんどのケースが「土葬」だとされています。華人やキリスト教系の人々も、歴史的に見れば、元々は土葬を選択する人が多くいました。
写真を見てもわかるように、インドネシアの中華系やキリスト教系のお墓は大きなサイズのものがほとんどです。この石の下に棺が埋められているわけです。
一方で、土葬ではなく火葬を選択する人は、そのほとんどがお墓を設けるのではなく、散骨をするか納骨堂に預けるかという二択になっているのが実情です。
納骨堂の場合

火葬を選ぶ人たちは、お墓を設けず、散骨するか納骨堂に預けるかを選びます。そのため今回ご紹介している「ヤヤサン・ゴトンロヨン」においても、広い納骨堂が用意されています。火葬された遺骨は、この納骨堂に安置することができるようになっているのです。
「ヤヤサン・ゴトンロヨン」の場合、納骨堂の利用料は1年間で30万~150万ルピアで、日本円ならば約2,300~12,000円(2019年5月時点)となります。納骨堂はロッカー式で、扉には故人の写真と共に名前(中国名とインドネシア名が併記できるようになっている)や生年月日・死亡日・火葬日が記されています。
遺族であれば遺骨は自由に取り出すことができます。お参りをする際には、ロッカーから骨壺を取り出し、近くに設えられた机に置いて故人を偲ぶという手順で行われます。

葬儀で用いられるインドネシアの棺の特徴は?

今度は「棺」に注目してみます。土葬の場合は棺のまま埋葬することになりますが、火葬の場合は日本と同じように、棺に入れた上で火葬をすることになります。
しかし日本と異なるのは、そのサイズと厚さです。火葬をするのであれば棺は焼却されてしまいます。そのため日本では「燃えやすい」ように、小さく、かつ薄いものが選ばれる傾向にあります。
しかしインドネシアの華人社会やキリスト教系の場合、土葬だけでなく火葬においても厚みのある重厚な棺が選ばれます。富裕層が土葬で使う特別な棺も含めてご紹介します。
キリスト教や仏教のデザインが彫刻された棺

「ヤヤサン・ゴトンロヨン」の葬儀式場の裏には棺だけが多数おさめられた倉庫があります。十字架や「最後の晩餐」などの絵画があしらわれているキリスト教徒向けのデザイン、あるいは、伝統的な中国画の彫刻が施されているもの、仏教徒向けのデザインの棺などが数多く展示されていました。遺族はここで棺を選択し、購入することができるようになっています。
棺の価格は主に板材の厚さで決まり、多くは5~10cm程度の厚さの板で制作されているようです。これらは土葬・火葬の両方で用いられます。厚い板で作られた棺も、火葬炉に入る大きさであれば、火葬に用いることができるのです。
棺の材料となる板は、無垢の木から作られたものと、化学物質を利用して作った合板とがあります。合板のものは価格が安いものの、燃えにくいことから火葬の際には時間がかかってしまうとの話でした。
アニメキャラクターがデザインされた子供向けの棺

中には、子供向けの棺もあります。アニメのキャラクターがデザインされていて、なかなかインパクトのある棺です。しかし、よくよく見てみると、もう何とも言えない気分になってしまうのが正直なところです。
こんなに幼くして亡くなるなんて・・・と悲しい気分にさせられるものがあり、これらの棺を用いた葬儀が来場者に与える影響にも大きなものがあるに違いありません。
しかし実際にこうした需要があるからこそ、こうした棺が用意されているということでもあります。悲しいことではありますが、厳然たる事実として「子供の死」が存在するという当たり前のことに、改めて想いを致すきっかけにもなりました。
富裕層が土葬で使う重厚な棺「シウパン」(壽板)とは?

また、富裕層向けの棺として「シウパン」(Siupan)というものがあります。主に華南で使われている伝統的なデザインの棺(中国語では「壽板」という)に相当するものです。一本の巨木をくりぬいて作成された、実に重厚な棺となっています。
なおこの棺については火葬炉に入りきらないため、土葬の場合にしか用いられません。30年経っても朽ちることがない耐久性を持つと言われます。ここで販売されている棺は、だいたい5億ルピア(約400万円前後)とのことです。
インドネシア華人社会の葬儀の特徴

続いては、華人社会の葬儀の特徴をいくつかご紹介します。私自身、華人インドネシア系の人間として、祖母の葬儀に立ち会いました。この写真は当時の様子を撮影したものです。2011年6月に行われたものです。
葬儀を自宅で行うケースと葬儀社で行うケース

「ヤヤサン・ゴトンロヨン」は葬儀式場を提供しているわけですが、遺族によっては自宅で葬儀を行うケースもあります。私の祖母の場合は葬儀場ではなく、自宅で葬儀を執り行いました。自宅で葬儀を行うケースもあれば、葬儀社で葬儀を行うケースもあるということです。

近年では家が狭かったり充分な駐車場が確保できない等の背景もあって、葬儀社で葬儀を利用するケースが増えているようです。
華人社会の葬儀の特徴は?

「ヤヤサン・ゴトンロヨン」の場合、葬儀はキリスト教式か仏教式のどちらかになるようです。正確な統計を取っていないようですが、おおよそ8割がキリスト教式、2割が仏教式とのことでした。葬儀の多くは、参列者が集まりやすい週末に行われるようです。
葬儀にかけられる予算にもよりますが、通常は数日程度にわたって行われるのが特徴です。但し、葬儀の期間中は、昼夜を通して常時儀式を行うのではなく、各日のうちの数時間だけに礼拝や法要を行い、葬儀の期間の最終日に出棺して火葬場または墓地に搬送するという流れになります(スケジュールのサンプルは後で紹介します)。

出棺に際しては、「気持ちの区切りをつけるため」という理由でスイカを割ったり、後述するような「まじない」の理由で食器を割ったりする風習もあります。
上の写真は葬儀式場で、キリスト教式葬儀で出棺を見送る遺族の様子です。左端の人物がスイカを持っており、このスイカは後に式場の前で割られることになります。スイカを割るのは、「もうこれでおしまい」という気持ちの上での区切りをつけるためだと言われます。
遺体保存の需要という現代的課題も

またインドネシアは国土が広い上、交通事情も必ずしも良くないため、葬儀を始めるまでの間の数日間、遺体を冷凍庫で保管したり、防腐処理(遠方に輸送しなければならない場合に限られる)を行ったりする場合もあるとのことでした。
この写真は、遺体を保管するための冷凍庫です。遺体は、棺に入れず、そのまま零下10度の温度で保管されることになります。インドネシアの場合、親戚が遠方や海外に住んでいるというケースもあります。当日や翌日に駆けつけるのは困難という場合もあるため、こうした施設が必要とされるようです。
なお、そうした事情から、保管機能だけを目的に「ヤヤサン・ゴトンロヨン」を利用する遺族もあるようで、この場合はイスラム教徒からの依頼になります。まさに現代的な需要だと言うことができそうです。
葬儀や火葬の日程を左右する「ジャワ暦」とは?

さらに、ジャワ島特有の特徴があります。それが「プラナタ・モンソ」(pranata mangsa)と呼ばれる伝統的な「ジャワ暦」の存在です。
特に仏教徒の場合は、日の吉凶を気にする場合が多く、それが葬儀の日程に影響を与えることになります。ジャワ暦には、日本でいうところの「六曜」があり、いわゆる「友引」に相当する日もあります。
この場合、その日の葬儀は避けるようにする遺族もあります。また、故人が「成仏」できないなどの災いを避けるため、例えば、柩の中に「これが芽を出すまでは連れて行くな」と言いながら(芽が出ることはない)焦がした豆を入れる、出棺の際に土器の茶碗を割る(同様の風習は日本の葬儀にも見られる)といったまじない事が行われることもあります。
これらはいずれも、故人が「迷って」、残された者を「連れて行かないように」するという意味を持ち、仏教徒に限らず、キリスト教徒の葬儀であっても行われる場合があるようです。似たような理由で、故人の眼鏡を柩に入れる場合は、「もう見ることができない」という意味で、壊してから入れられます。
なおエカワティさんがかつて担当した葬儀の際、こうしたまじないことを「そんなの迷信だよ」と受け付けなかった遺族がいたそうです。その数ヶ月後、またその遺族が葬儀場にやってきたため、どうしたのかとエカワティさんが聞くと、「実は、また親戚が一人亡くなりまして」というエピソードも教えていただきました。
イスラム式との違いは「24時間制限」

こうした諸事情で、被葬者が亡くなった後、葬儀が始まるまでの間には一定の期間が空けられる場合が多くあります。「24時間以内に遺体を埋葬しなければならない」とするイスラム教徒の葬儀とは対照的です。
また、インドネシアの法律では、「遺体を外気に晒すことができる期間は24時間まで」と定められており、納棺した後は棺の蓋を開けることができません(24時間を超えてしまうため)。
このため、例えばキリスト教式の葬儀の場合、2日目に柩の蓋を閉める儀式が設定されており、それ以降は柩の蓋は閉められたままで儀式が進行します。
あるキリスト教系の家族のケース

最後に、葬儀の流れとして、あるキリスト教系の家族のケースをご紹介します。2019年1月4日の夕方17:57にマランで亡くなった華人系インドネシア男性(私の遠戚)のケースです。
亡くなってから火葬するまでのスケジュール
・1月 4日17:57 : 死亡・マランにあるPanti Waluya Sawahan病院にて
・1月10日18:00 : 精神のお祈り(死の7日後)Doa arwah・・・通夜
・1月11日 9:00 : 棺を閉める儀式(Upacara tutup peti)・・・納棺の儀式
・1月11日18:30 : 言葉の崇拝(Ibadat Sabda)・・・葬儀ミサ(ことばの典礼)
・1月12日18:00 : 花の夜の崇拝(Ibadat Malam Bunga)・・・献花の儀式
・1月13日 8:00 : 火葬場へ遺体が出発する儀式(Upacara pemberangkatan Jenasah)・・・出棺の儀式
・1月13日 9:30 : 火葬の儀式(Upacara kremasi)・・・火葬
・2月12日18:00 : 40日忌(acara 40 hari)
日本では、通夜と告別式(葬儀)の2日で終わりますが、インドネシアのキリスト教式の葬儀は1週間近くの長い儀式となっています。
宗教とは無関係に「中国系」としての共通点も

ただ、宗教とは無関係に、中国系の葬儀の場合、「1週間」という単位は、他の国々で行われる葬儀とも共通しているようです(少なくともシンガポールでは1週間)。
1週間(程度)の間に、カトリック教会で定められているプログラムを、飛び飛びで行われるためではないかと推察されます。一方で日本の場合は、全部を通して行うということかと思います。
インドネシアにおける火葬の実態とは?
というわけで、今回のブログでは「インドネシアの葬儀|非イスラムのキリスト教系の葬式と火葬の内容は?」と題して、インドネシアのキリスト教形式での葬儀をご紹介しました。
3部構成でまとめていますが「葬儀」の次は「火葬」です。
| タイトル | |
|---|---|
| 第1部 | インドネシアの葬儀|非イスラムのキリスト教系の葬式と火葬の内容は?(本ページ) |
| 第2部 | インドネシアで火葬場見学|東ジャワ・マランのキリスト教華人の場合 |
| 第3部 | インドネシアの火葬事情|イスラム土葬文化で火葬が選ばれる背景と課題 |
続いての第2部では、「インドネシアで火葬場見学|東ジャワ・マランのキリスト教華人の場合」と題して、インドネシアのキリスト教形式での火葬場の実態をご紹介します。ぜひご覧ください。













